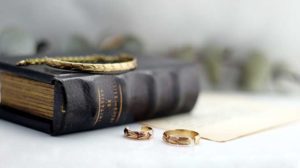イヤーカフ は 着ける 場所 によって 意味 があるといわれています。
遡ること中世ヨーロッパでは男性は左耳に、女性は右耳にピアスを着けるとされてたため、これが元となり現代ではイヤーカフも男性は左耳、女性は右耳と言われるようになったようです。
ですがアイテムがピアスからイヤーカフになって、中世ヨーロッパから現代になった今も、同様に考えられるでしょうか?
イヤーカフを着ける場所と意味の元となったピアスの歴史から、紐解きます。
もくじ
【 はじめに 】

withコロナ時代となり、マスクを着けて過ごす生活でファッションも大きく変化してきています。
マスクをしていても邪魔にならないようなアクセサリーに注目が集まり、その流れに後押しされて耳のふちに引っ掛けるタイプのイヤーアクセサリーである「イヤーカフ」が人気を博しています。
そんなイヤーカフですが、着ける場所によって意味が違う、といった情報も流れています。
これは半分本当で半分嘘、とも言えることなんです。
殆どのサイトはピアスの歴史から引用して、イヤーカフの意味合いとしています。
中世ヨーロッパではそのように考えられていたということを、現代に置き換えているんですね。
しかし中世ヨーロッパで言われていた事が、現代の私たちにも当てはまるでしょうか?
今回はピアスの歴史を踏まえたうえで、イヤーカフについてご紹介していきたいと思います。
【 ピアスの歴史 】

アイスマンを知っていますか?
アイスマンはオーストリアの氷河から見つかった5300年以上前のミイラです。
そしてピアスを身に着けていたであろう男性で現存する最古の人。
そう、彼の耳にはピアスを着けていた形跡が残っているんです。
そんなに昔のミイラから、そんなことがわかるなんてなんともロマンがありますね。
ピアスの他の記録を探ってみると、約3600年前の古代エジプト文明では王族の男性がピアスを身に着け、その後のバビロニア帝国などでは王侯貴族や兵士などが地位の象徴としてピアスを着けていた記録があります。
古代ギリシャでは装飾目的よりも魔除けとして男女ともにピアスを着けていたという記録もあります。
片耳にピアスを着けるというスタイルは、ちょうどこのころに生まれたとか。
▷アクセサリーの歴史について詳しく知りたい方はコチラをどうぞ→

そして現代よく耳にする「男性は左耳にピアスを着ける」という慣習は、中世ヨーロッパに生まれたのです。
中世ヨーロッパは騎士道を重んじていました。
この騎士道に由来するマナーとして有名なのはレディーファースト。
この頃の男性は女性の身を守るという役目があったのです。
そのため男性は女性と並んで歩く際は必ず女性の右側を歩いて、何かあった場合にも利き手(この場合右手)で女性を守ることができたといいます。
そして女性を守る勇気の証として、男性はピアスを身に着けていたのです。
男性のピアスは守る女性に近い方の左耳に着け、対になるもう片方のピアスは守られる女性の右耳につけるのが一般的だったとか。
この慣習が少々形を変えて現代に残っているのが、「男性は左耳にピアスを着ける」といった風習。

男性のピアスの着ける位置について調べると、さきほどの左耳とは逆に、男性が右耳にひとつだけ着けるのは「同性愛者」と思われるといった記事を見かけることがあります。
これは中世ヨーロッパの風習である「守る人=男性」は左耳、「守られる人=女性」は右耳にピアスをつけたことが拡大解釈され、そのようになったと思われます。
ですが、これを真っ向から信じる人や、そのように考える人が現代にどれだけいるでしょうか。
それに中世ヨーロッパの考え方ですら、現代では知らない方の方が多いと思います。
古代から存在するピアスの役割は地位の象徴であったり、魔除けでした。
現代ではお守り感覚で使う方はいらっしゃるかもしれませんが、主な役割はファッションであり、装飾品です。
ファッションとして見た場合、過去の謂れを気にするよりも、格好いいか、格好悪いかでしかないと思うのです。
現に今の私たちのファッションは、ボーダーレス化が進んできています。
女性だから、男性だから、といった考え方時代が通用しなくなってきていますよね。
ピアスも日本で一般的になってきたばかりの頃は、着ける位置や数を気にしたり、片耳は同性愛者だと思われるといった話が流れたこともありました。
ですが現在では、どうでしょう?
そういったことを気にして着けている人がどのくらいいるんでしょうか。
誰もが好きなように、楽しんでいるといった印象の方が強いと思うのです。
アクセサリーやピアスの歴史を知ることは大切ですが、過去の考え方がずっと通用するかというとそうではないですよね。
アクセサリーも時代とともに変化しています。
過去にはピアスも着ける個数や位置に関して様々な謂れがありました。
ですがファッションアイテムのひとつになった今、それぞれに自由に楽しんでいますし、それこそがファッションアイテムの醍醐味でもあるのです。
【 イヤーカフの歴史 】

耳に着けるアクセサリーの歴史を辿ると、日本ではイヤリングが長いこと主流でした。
日本におけるイヤリングの文化は約6500年前の縄文時代に確認されています。
この頃にみられたものは主に玦状耳飾りや耳栓(じせん)と呼ばれるもので、石や粘土で作られていました。
この玦状耳飾りというのが、イヤリングのような、今でいうイヤーカフのような、そんな形状をしています。
◇玦状耳飾りの写真はこちらをどうぞ→
弥生時代になるとイヤリングの文化は衰退して、古墳時代中期~後期に金属製装身具の製法が流入したことで再び日本でもイヤリングが作られたようです。
しかし飛鳥時代以降、唐風文化の波及などによりイヤリングは衰退したと考えられ、明治時代になるまで一般的ではなくなったといわれています。

その後時が流れ1980年代頃から日本では徐々にピアスが普及し始めます。
1990年代には耳にいくつもピアスを開けたり、ピアスのホールを拡張したりすることも流行しました。
イヤーカフの正式な記録はありませんが、ピアスが普及し始めた時代にもイヤーカフは存在しました。
しかしピアスの人気に押されてか、一時期ほとんど姿を見なくなったのです。
そんなイヤーカフが改めて本格的に広まり始めたのは2015年頃から。
ピアッシングに抵抗があったイヤリング派の方たちに受け入れられた事が大きかったのと、コロナの流行がおこりマスクの着用が必須となったことなどが追い風となりました。
イヤリングは耳たぶに挟むイヤーアクセサリー。
ピアスは耳たぶに穴を開け(ピアッシング)その穴に通すタイプ。
(英語でpierceというのは、穴を開けるという意味。
そのため海外では耳に着けるアクセサリーは基本的には全てearringと言います。
どうしても区別するような場合にはピアスの事をpierced earringというような場合もあります。)

一方今回の主役であるイヤーカフ。
「ear cuff」のcuffというのは襟や袖口、カフスの事を指します。
イヤーカフと一言で言えど、タイプは様々。
耳のふちに挟んだり引っ掛けて装着するものをイヤーカフと呼び、耳の後ろからかけるタイプをイヤーフックと言います。
耳に挟むタイプはイヤークリップと呼ばれたりもします。
ピアスやイヤリングとの一番の大きな違いは、この耳への装着方法です。
イヤリングとは少し似ている部分もありますが、イヤリングは耳たぶに挟みますがイヤーカフは耳たぶ以外にもつけられるのが嬉しいですね。
◇イヤーカフを使う時に気を付けたいことはコチラをどうぞ→
【 あなたはどう着ける? 】

イヤーカフは基本的には1個ずつ販売されています。
これは絶対に片耳にしかつけてはいけないという訳ではなく、アシンメトリーに着けること、レイヤードすることを前提にしているため。
両耳にピアスをして、片耳にイヤーカフを追加する、イヤーカフを片耳だけに1~2個着ける、そんな風にアシンメトリーを意識することで洗練された印象になります。
しかしイヤーカフを通常のピアスと同じような耳たぶに近い位置にひとつだけ着ける、といったつけ方をすると、片側だけピアスを落としてしまったように見えたりもしますのでそういった際は着ける位置やデザインに注意です。
イヤーカフの強みは、イヤリングやピアスには難しい凝ったデザインを活かせるところ。
横顔だけでなく、斜め後ろからなど、見る角度によってイメージも変わります。
ゴールドカラーとシルバーカラーを合わせて着けたり、ピアスやイヤリングとレイヤードしたり…。
ルールにとらわれずに自由な楽しみ方ができるのがイヤーカフです。
同じイヤーカフでも耳のトップに近い場所に着けるのと、下側に着けるのでは印象も大きく変わってきます。
ひとつでも何通りも楽しめるなんて、コストパフォーマンスも高いですね!
場所によってはマスクの着脱にも邪魔にならないですし、ピアスの穴の有無も関係ないのでちょっとしたプレゼントにもおススメです。

こんなにもいいことずくめのイヤーカフ。
ですが1点だけ気を付けてもらいたいことが…。
先ほどのピアスの歴史についてご紹介した際に少し触れましたが、海外では耳のアクセサリーの位置について敏感な方たちが多いです。
ファッションとして、自己表現としてはご自身の好きな位置に好きなように着用することが大事です。
しかし残念ながら海外ではご自身の意図とは、ズレた表現になってしまうことも…。
これは宗教的なモチーフのアクセサリーの場合もしかり、です。
(宗教モチーフに関してはとてもセンシティブな一面もあります。
ご自身の信仰とは別のモチーフを身に着けていたり、訪れた土地とモチーフの関係性、相性、歴史などで海外ではよく思われないといった事例もあるので海外に行く際はご注意を…。)
参考までイヤーアクセサリーのNG例を記載しておきますので、海外に行く際は少しだけ思い出していただけたら幸いです。
海外でNGとされること
・女性が耳のアクセサリーを左だけに着ける(同性愛者であるとみられる場合がある)
・男性が耳のアクセサリーを右だけに着ける(同性愛者であるとみられる場合がある)
海外でOKとされること
・女性が耳のアクセサリーを右にだけ着ける(優しさや成人女性の証)
・男性が耳のアクセサリーを左にだけ着ける(勇気とほこりを象徴)
【 まとめ 】

イヤーカフ を 着ける 場所 と 意味 をご紹介してきました。
現在言われているイヤーカフを着ける場所の意味合いは、中世ヨーロッパのピアスの着け方からきていました。
ですがピアスやイヤーカフのようなイヤーアクセサリーがファッションアイテムとなった今、すでに着ける場所に決まりはなくなってきています。
ご自身の好きなように、好きな位置につけて様々な楽しみ方をしてもらいたいアイテムです。
とはいえ日本ではそうでも、海外に行くとそうは思わない方もまだまだいらっしゃいます。
郷に入っては郷に従え、といった言葉もありますが、その土地ごとの風習や考え方などもありますので否定したり関係ないと考えるのではなく、お互いを尊重しながら広い視野で文化に触れることができるといいですよね。
もし海外に行くような際には少しだけイヤーアクセサリーのつけ方にご注意くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
◇似合うアクセサリーの形に迷ったら、こちらもどうぞ→