アクセサリー モチーフ ごとに昔から伝わる願いや意味合いがあります。
ここではモチーフに込められた願いを歴史を紐解きながら解説していきます。
またリングやネックレス、ピアスやブレスレットが太古の昔に担っていた役割も一緒にご紹介しています。
もくじ
【 はじめに 】

私たちが何気なく身に着けている指輪やネックレス、ピアス。
アクセサリーとして生活に溶け込んでいる存在ですが、元々は一つ一つに「役割」が与えらていた時代もあります。
現在はお洒落を楽しむ一つのアイテムとして身近になっていますが、アクセサリーの起源は意外と知られていないかもしれません。
洋服などと違って、身に着けなくてもいいアイテムだけどなぜか着けたくなったり…身に着けていないと落ち着かない、そんな特別なアクセサリーがある方もいらっしゃると思います。
必然ではないはずのアイテムでありながらも、ないと何だか物足りない…。
ここではそんな存在であるアクセサリーの起源を辿りながら、アクセサリーモチーフに込められた意味や役割を見ていきたいと思います。
【 起源を辿る 】

時を遡ること、古代エジプト時代。
樹液や泥などを使い体に模様を施し装飾をしたことがアクセサリーの起源であると言われています。
この時代ではどうやって体を隠すか、ということよりも先にどんな模様で体を装飾するかといったことが重要だったようです。
時代が進んでいくと、動物や魚の骨や歯、鳥の羽、樹木や木の実、貝、小石などなど…様々なもので自身を飾るようになります。
このあたりだけ読むとちょっとだけ、怪しげな儀式を思い浮かべた方もいらっしゃるのではないでしょうか…。
そうです。
でもそれ、ほぼ正解です。
アクセサリーは魔力が籠ると信じられていたために、悪霊や外敵から身を守る手段として、まじないや魔除けの一種として身に着けられていたわけです。
ですのでそういった儀式にももちろん使われていました。
また戦利品を身に着けることで自身の強さをアピールしたり、強い獲物を捕まえたことを誇る意味合いなどもありました。
そして種族で似たデザインのアイテムを身に着けることで絆を表現したりもしたようです。
そういった狩猟や遊牧の生活から農耕民の生活になるころには社会秩序が産まれ、古代文明が登場します。
学生時代の歴史の授業をぼんやりと思い出す方もいるかもしれませんが、移動しながら生活していくのではなく、水辺に集い自然とその場所で農業や畜産をすることで、水のある場所には豊かな文明が築かれます。
文明が築かれていくと共に生活の中で水辺に堆積する資源(金や貴石)を見つけ、資源を見つけることで、加工する術が発展していきます。
【 アクセサリーの持っていた意味 】
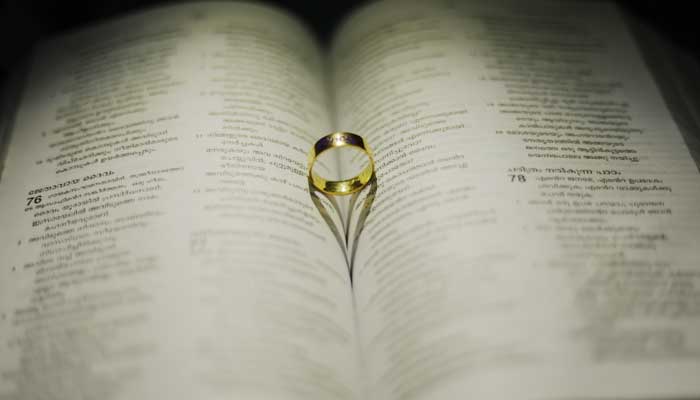
アクセサリー がどうやって発展していったのかをざっくりと書いてきましたが、個々のアイテムにもモチーフごとにそれぞれ「役割」があったようです。
例えば、こんな風です。
■ネックレス

アクセサリーの中では世界最古の装身具と言われています。
狩猟時代は自身の強さを示すためにも仕留めた獣の牙や骨を紐に通し首飾りとしましたが、強さの象徴から段々と狩猟の成功や豊作を願うお守りのようなアイテムになっていったと考えられています。
日本の古墳時代には水晶や翡翠、瑪瑙などが使われたネックレスを男女問わず身につけていましたが、権力の象徴、お守りとして使われていたようです。
■ブレスレット

意外にも歴史の古いブレスレット。
ネックレス同様、最古の装身具と言われています。
動物の骨や貝殻は穴を開けてブレスレットの形状につなぎ合わせ、装飾品というよりは非常に高価なもの、現代のお金のような立ち位置で使用されていたようです。
■ピアス

古の時代、悪魔や病は体の穴から入り込んでくると考えられていました。
そのためそれを防ぐために耳の入り口にピアスを施しました。
ピアスは魔除け以外にも身分を証明するためだったり、願掛けの一種であったりもしました。
耳たぶの飾りは知恵や幸運を呼ぶという言い伝えもあります。
■指輪

指輪もピラミッドの中からも発見され、紀元前の古代エジプトで既に使われていたといわれています。
その時代での指輪は印鑑としてだったり、契約、服従の証明として使われていました。
また神秘的な力のあるアイテムとして魔除けとして身に着けたと言われています。
現代でも名残が残っているものとしては、指輪を着ける指によって意味合いがあるというもの。
結婚指輪などはその代表的な物ですね。
古代ギリシャ人の言い伝えでは、左手の薬指が心臓と直結している(一番近いところにある)とし、心臓の中にはその人の心があると信じられていたといいます。
◇着ける指ごとの意味合いを知りたい方はコチラをどうぞ→
【 モチーフに込められた意味 】
海外では様々な想いや願い、意味を込めたモチーフアクセサリーもたくさんあります。
これは形にできない想いを伝えるためにこういったモチーフが産まれたとも言われていて、現代でもお守り感覚でアクセサリーを選ぶ方も多いです。
あなたが着けているお気に入りのアクセサリー も、もしかしたら知らないだけで意味があるモチーフかもしれません。
ポピュラーなものをご紹介していきますので、ぜひ読んでみてくださいね。
■鍵(キー)
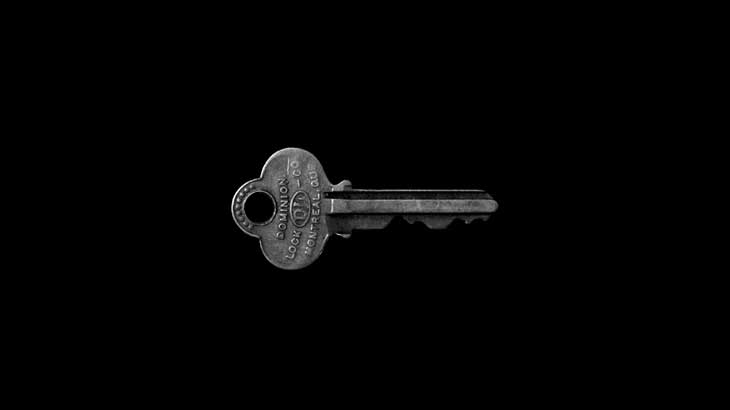
鍵は自宅の入り口を象徴することから繁栄を意味するといわれています。
ヨーロッパでは古くから、鍵を身に着けることがあり、それは希望や可能性、幸運の扉を開ける、閉ざされた心を開くといった意味で身に着けられました。
鍵のアクセサリーは幸運や魔除けのシンボルとして現代でもよく使われています。
■リボン
人と人を結ぶ、絆を深める縁結びの象徴とされています。
絆や約束といった意味合いのモチーフ。
■王冠(クラウン)

名声、富、栄光、権力など、最高の地位を象徴し、すべての幸福を表現しています。
勝利をもたらすとも言われているため、お守りとして身に着けられることも多いようです。
■錨
錨といえば船を固定し荒波から守るもの。
そのため安定や希望、力のシンボルとされています。
荒波から身を守る、ということで商売繁盛のモチーフとして、また恋愛においては離れ離れにならないように、揺れ動くことなく進む方向へ導くといった意味もあるようです。
■馬蹄(ホースシュー)

海外でポピュラーなお守りのホースシュー。
馬の蹄に釘で固定する馬具のひとつ。
蹄に装着する時、内側4本・外側に3本の釘が使われます。
釘の本数は合わせて7本になるので「ラッキーセブン」ということで、幸運のお守りであると考えられています。
一般的には上向きのU字型が幸運を逃さないと言われています。
家庭運が上がるモチーフとして人気があります。
※ホースシューが「上向き」と「下向き」では意味合いが違ってきます。
・上向き
U字型になっている状態のホースシュー。
U字のくぼみ部分で「幸運を受け止める」という意味があるそう。
どんどん幸運を溜めていくことができると考えられているようです。
・下向き
U字型が逆向きになっている下向きのホースシュー。
下向きだから幸運を溜めることができない訳ではありません!
U字が逆の場合は「不運を落とす」といって、厄除けの意味合いがあるんです。
■羽(フェザー)
羽と言えば空を飛ぶ鳥を連想しますね。
そのことから上昇や飛躍の象徴とされている羽。
能力や長所を高め飛躍、躍進させると言われます。
■鳩
平和のシンボルである鳩。鳩がそう呼ばれるようになったのは、ノアの箱舟から。
鳩がオリーブの葉を銜えて地球が無事であることをノアに知らせたことから来ています。
■蝶

蝶は変身、復活のシンボルとされています。
言わずもがな、幼虫からさなぎ、さなぎから成虫に変化することに由来しています。
また羽ばたいて飛ぶことから飛躍や上昇、新しい道を切り拓くといった意味合いも。
■トカゲ(ヤモリ)
トカゲは生き延びる為に自ら尻尾を切っても再生する力を持っています。
そのことから不死や大願成就のお守りと言われています。
知恵や適応性を象徴するモチーフです。
■カエル

無事に帰る、福がかえる、災いをかえる、幸運がかえる、お金がかえる、若返る、などなど書き出すとキリがないほど…。
幸運のシンボルの代表です。
■蛇
古来より幸運や吉兆、永遠の象徴とされています。
蛇がとぐろを巻く様子は終わりのない輪のように見えるため、「不滅の愛」のシンボルとされ、恋人に贈る定番デザインだったようです。
また神の遣いとして崇められいて、家や財産の守り神とも考えられています。
■天使

もはやだれもが知っている、説明不要のモチーフ。
神の使者である天使は「想いを伝えてくれる」と考えられていたようです。
愛を取り持つキューピッドとしてお守りに使われてきました。
■心臓(ハート)
命、幸せ、愛情の象徴とされています。
また恋愛成就や幸せな結婚への願いが込められているといいます。
■十字架(クロス)

キリスト教の象徴として有名なクロスモチーフ。
生命力の象徴・復活・永遠といった意味を持っていて、災いから身を守るとされています。
また人が手を広げた形にも見えるということで、解放という意味もあるようです。
(宗教モチーフに関してはとてもセンシティブな一面もあります。
ご自身の信仰とは別のモチーフを身に着けていたり、訪れた土地とモチーフの関係性、相性、歴史などで海外ではよく思われないといった事例もあるので海外に行く際はご注意を…。)
■髑髏(スカル)

一見不吉な象徴にも見える骸骨ですが、実は復活や再生を意味します。
人間の魂は頭部に宿るという考え方から、頭蓋骨や頭部は古の時代か戦利品とされていました。
そのため直接的な死という意味合いよりも、繁殖や生命の源といった意味合いが強くなったようです。
■ティアドロップ
ハワイなどでは乾いた大地に降る恵の雨を、神々の流す涙のしずく(ティアドロップ)と呼んでいて、生きるエネルギーの源を意味します。
また悲しいみや辛さの涙が、感動や喜びの涙に変わりますようにという願いも込められているそう。
■月(ムーン)

しばしば月は女性に例えらることがありますが、月は女性らしさや成長のシンボルです。
心に落ち着きを与えるといった意味もあるようです。
古くから悪を封じる記号として用いられてきたため、身を守るお守りとしての意味があります。
また、暗い夜空に光輝く星は、希望・光の象徴として、チャンスの訪れや、幸せの扉を開いて、健康や冨などの幸せを呼び込むモチーフとされています。
■星(スター)
希望や光の象徴とされ、チャンスの訪れや健康・富・幸運を呼び込むモチーフとされています。
夜空に光り輝く星は希望にも例えられることがあるので、そのように言われるようになったようです。
■四つ葉(クローバー)

言わずと知れた幸福のモチーフ。
元々、4つの葉はそれぞれfaith(誠実)、hope(希望)、love(愛)、lucky(幸運)の意味を持っているとされ、それらを呼び込むと言われています。
十字架(クロス)と形状が似ている為、魔除けの意味もあるようです。
■月桂樹(ローレル)
あまりピンとこない方も多いかと思いますが、オリンピックメダルなどに描かれているあの葉っぱ。
勝利や栄光を表し、褒めたたえるといった意味もあります。
言われてみると競技の表彰なども含め、そういった場面によく使用されるモチーフですね。
■花(フラワー)

いわずと知れた幸せのシンボルで、美しさや女性らしさを意味します。
愛情や良縁を呼び寄せると言われることも。
◇花ごとの詳しい意味合いはコチラをどうぞ→
■アラベスク(唐草模様)
つるが絡みたくましく伸びる様子はまさに生命力や長寿の象徴。
互いに絡み合うデザインなので強い絆や永遠の愛を象徴することも。
■ バラ(薔薇)
ギリシャ神話では愛と美の女神であるアフロディーテが誕生した際に神々が咲かせたのがバラと言われています。
ヨーロッパでは結婚祝いにバラで編んだ冠を贈る風習があるところも。
愛を象徴する代表的なモチーフです。
■ツバメ

ツバメは夫婦そろって子育てをするので、その様子から「長く幸せな家庭を築く」シンボルになっています。
またヒナたちに食べ物を運ぶ姿から、「幸せを運ぶ鳥」とも呼ばれます。
■ ふくろう(アウル)

日本では「福来郎」(福が来る)、「不苦労」(苦労しない)、「福籠」(福がこもる)などと書かれ縁起の良い鳥とされてきました。
夜目がきくことから見通しが明るい、首が360度回ることから首が回らない(借金で支払いができない)の逆の意味として考えられ、開運や招福、商売繁盛に用いられました。
■ミツバチ(蜂)
昆虫の中でも人気のあるミツバチのモチーフ。
古代ギリシア時代より縁起の良いものとされています。
ヨーロッパではミツバチの来訪は、未知の良いお客様の来訪を告げるとされました。
そのほかにも、勤勉、純潔、豊穣、知恵のシンボルでもあります。
■てんとう虫

太陽に向かって飛んでいく様から太陽神である「天道」の名前がついたてんとう虫。
太古の昔から幸運の象徴と考えられてきました。
■ ドルフィン(イルカ)
イルカはとても優しい生き物。
優しく感受性が豊かなイルカのように、感受性や直感を高めてくれるシンボルとして人気です。
■猫(キャット)

古代エジプトではお守りに猫の絵が描かれていました。
魔除けや幸運を引き寄せるモチーフとして古来から親しまれていたのです。
日本でも招き猫として使われているように、良い運を引き寄せ、悪い運を追っ払ってくれると考えられてきました。
猫は自由気ままな印象もあるので、自由を象徴するモチーフでもあります。
■ウサギ
ウサギはとても子だくさん。
そのため繁栄の象徴とされます。
また飛び跳ねるその様子が飛躍を連想させます。
長い耳をもっているので、長い耳でよく聞くことで福を集める、出世運・財産運を上げると考えられています。
■ リンゴ

アダムとイブの話にもでてくるりんご。
愛することや信じる事、分かち合うことを教えてくれる象徴。
ギリシャ神話ではゼウスとヘラが結婚する際に大地の女神ガイアが黄金のりんごのなる木を贈ったことから、美と愛のシンボルとも考えられています。
■イニシャルや数字
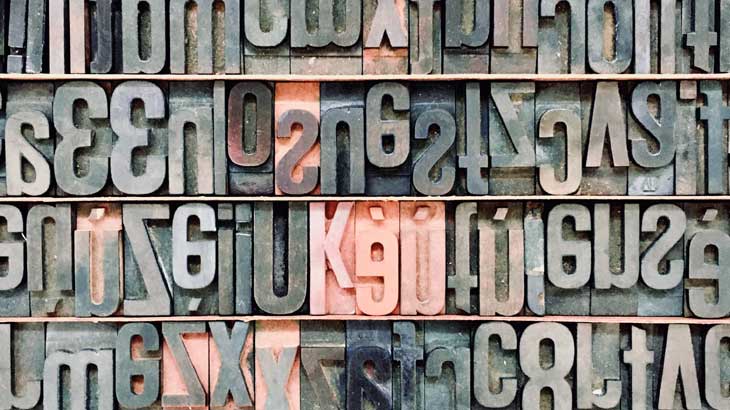
イニシャルは誰にとってもそれぞれに特別な意味を持ちます。
ご自身のものはお守りとして、恋人や親族などのイニシャルはその人との絆を深めるとも。
イニシャルや意味のある数字は運気アップや絆を深めるモチーフとされています。
◇これ以外のラッキーモチーフ「スプーンリング」についてはこちら→
【 まとめ 】

アクセサリー モチーフに込められた願いと歴史をご紹介してきました。
アクセサリーは現代では衣食住に不可欠であるとは決して言えません。
しかし文化や慣習、歴史の中で重要な役割を果たしてきたものです。
現代では古代のような魔除け的な意味合いでなくとも、身に着けていないと落ち着かないとか、ゲン担ぎといった意味で身に着けている方もいると思います。
アクセサリーをお守りのように感じる心は、古の時代から引き継がれてきた気持ちなのかもしれません。
いままで使っているお気に入りのアクセサリーも、起源やモチーフの意味を知ると、今までとはまた違った、新鮮な気持ちで身に着けられるかもしれませんね!
現代ではお守りや魔除けまでいかずとも、身に着けることで気持ちが明るくなる、背筋が伸びるような気持ちになる、そんな自分自身の気持ちの切り替えスイッチになるような、そんなアクセサリーに出会えたら素敵ですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!








