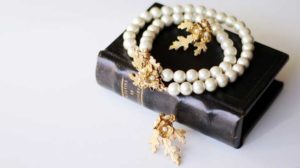そもそもクリスマスってなんでお祝いしているのか知っていますか?
クリスマス に プレゼント や アクセサリー を贈る背景をご紹介していきます。
もくじ
【 はじめに 】

クリスマス に プレゼント を贈るのはなぜ?
12月になれば街はツリーや電飾でキラキラと飾られ、どこからかクリスマスソングが流れてきます。
そんな雰囲気を見ていると、子供から大人まで、なんとなくわくわくした気持ちになりますよね。
今年のクリスマスは誰に何を贈ろうか、とか、今年のクリスマスケーキは何にしようとかツリーの飾りつけは…嬉しい悩みは尽きません。
プレゼントを交換したりディナーやケーキを楽しむそんなイベントのようなクリスマス。
なんとなくイエス・キリストの生誕祭、だと思いながらも、キリスト教以外の方でも祝っていますよね。
でも正確にはどんな記念日なのか、詳細を知っている人はなかなかいないと思います。
今回はそんな クリスマス と プレゼント や アクセサリー を贈る慣習についてご紹介していきます。
【 クリスマス ってどんな日? 】
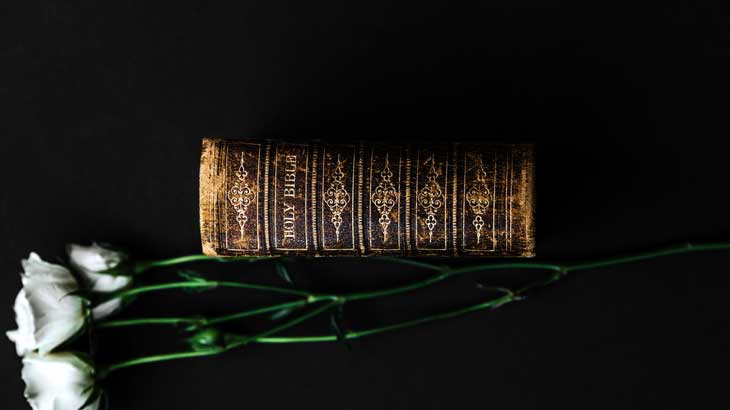
クリスマスとはいったいどんな日?
クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う日。
キリスト教では正確には「降誕を祝う日」ですね。
キリスト教の中では復活祭と共にクリスマスは特別とされています。
ここで大切なのは「誕生を祝う日」であって、「誕生日」ではないのです。
どっちでもいいのでは?と思う方もいらっしゃると思うんですが、生まれた日と、生まれたことをお祝いする日、を細かに分けているのは、新約聖書でもイエス・キリストの「誕生日」については言及されていないからなんです。
紀元前という表記はBefore Christ、略してB.Cと表記します。
これはキリスト生誕の前か後かということですが、西暦1年をキリストの降誕年とする決まりがあったから。
そのためマタイ福音書などから推察して表記されたというのですが、現在でも正確な降誕日はわからないのだそう。
ではなんで12月25日にクリスマスを祝うことになったのでしょう。
これは有力な一説には、ミトラ教が大きく影響しているようです。
キリスト教は聞いたことがあっても、ミトラ教って聞いたことがある人はほとんどいないのではないでしょうか。
それもそのはず。
2世紀~4世紀にかけての古代ローマで太陽神ミトラスを崇めていたのがミトラ教なんです。
古代ローマはあらゆる異教の文化を吸収しながら領地を広げていきました。
そのため元々はイランやインドで盛んだったミトラ教も吸収・浸透した文化・宗教の1つなんです。
そのミトラ教の慣習の中に、冬至の終わりの日である12月25日に太陽の復活を祝う、というものがあったそうです。
ミトラ教が古代ローマに入ってくる前は、農耕の神であるサートゥルヌスを祝う冬至の祭りがありました。
これは12月17日に行われていたようですが、ミトラ教が入ってくるとサートゥルヌスを祝う祭りと、太陽の復活を祝う祭りをあわせて1週間ほど宴が続いたと言われています。
そして時は流れて313年にミラノ勅令によりローマはキリスト教を公認、392年にキリスト教国となったのです。
その後冬至のお祭りを引き継ぎ、12月25日にイエス・キリストの降誕を祝うようになったと言います。
現代の私たちが楽しんでいるクリスマスの習慣であるクリスマス特有の食事や、プレゼントというのは、先ほど出てきた古代ローマの冬至の祭りの習慣の1つだったと言います。
ですので古代ローマの冬至の祭りと、ミトラ教の太陽の復活を祝う祭りを、ミックスして引き継がれたものがクリスマスなんです。
そういうとキリスト教が美味しいとこ取りしたようにも聞こえてしまいますが…
実際に聖書を読んだことがある方であれば、なるほどと理解できる部分もあるかもしれません。
聖書の中で重要なキーワードの1つである「復活」という言葉。
聖書ではイエス・キリストは私たちの罪を贖うために犠牲となった後復活します。
そして古代ローマの人も含め他の様々な文献では、太陽は冬至に一度死んでから復活をすると考えられてきました。
冬至の日に太陽の復活を見ることで、キリスト教の方たちはイエス・キリストの復活に思いを馳せたのかもしれませんね。
このあたりは文献等の確認がとれないのであくまでも私個人の推測の域を出ませんが、そう考えれば冬至の祭りが時を経てイエス・キリストの降誕を祝う日になったことも何となく理解できるような気がします。
何にせよ古代ローマの人々が異教の文化を迫害したり除外するのではなく、吸収する寛容さがあったからこそ、現在の形のクリスマスが出来上がったんですね。
【 クリスマスとプレゼント 】

クリスマスプレゼントのはじまりは…
クリスマスの起源であるとされる有力候補の冬至の祭りでは、特別な食事やプレゼントをする習慣がありました。
正確な記録は残っていないため言い切ることができませんが、この習慣は多かれ少なかれクリスマスプレゼントに影響を与えていると考えられています。
由来していると考えられるお話しをいくつかご紹介していきます。
・東方の三賢者(東方の三賢人)

ここで外せないのはキリスト教の新約聖書にある東方の三賢者(東方の三賢人)のこと。
イエス・キリストが誕生した夜、東方で星を見ていた占星術の学者たち(賢者、博士や学者と訳されることもありますが、本来人数についての正確な明記はありません)は遥か遠くに「見たことのない星」を見つけ星の下を目指して旅を始めます。
その後その星がユダヤ人の王が産まれたことを告げるものだと理解した学者たちは、星に導かれベツレヘムの地で母マリア、幼子イエスと出会います。
その時賢人たちがイエスに捧げたのが、乳香(祈りの象徴。フランキンセンスの樹液を固めたもの、古代エジプトの時代には神にささげる香りとして珍重されていました。)、没薬(死の象徴。樹木から分泌される、赤褐色の植物性ゴム樹脂。ミイラなどの遺体の防腐処理として使用されることもあります。)、黄金(王位の象徴)の贈り物であったと言います。
◇乳香を詳しく知りたい方はこちらをどうぞ→
◇没薬を詳しく知りたい方はこちらをどうぞ→
この贈り物の数が3種類であったことから、賢人の数が3人であると考えられ、東方の三賢者(東方の三賢人)と言われるようになりました。
またこの賢人を導いた星は「ベツレヘムの星」(預言書(ミカ書5章1節))と呼ばれ、クリスマスツリーのてっぺんに飾る星のモデルになっています。
クリスマスプレゼントも元をたどると、イエス・キリストの誕生を祝う贈り物になぞらえているんですね。
・実在したサンタクロース

サンタクロースのモデルとなった聖ニコラオ(ニコラウス)(270年頃~345年もしくは352年)。
キリスト教の司教であり神学者だった人物です。
この方はローマ帝国リュキュア属州のミラで大主教をつとめました。
商人の娘が貧しさのあまり身売りしなければならないという噂を耳にしたニコラオ(ニコラウス)は、夜中にコッソリと商人の家の窓から金貨を投げ入れたのです。
そしてその金貨が暖炉の近くに干してあった靴下にはいったと言われています。
こうして娘たちを救ったニコラオ(ニコラウス)の名前が、オランダ語を経由し「サンタクロース」となったのだとか。
オランダでは聖ニコラオ(ニコラウス)の命日である12月6日には彼を偲んでお祝いをし、子供たちにプレゼントを贈るそうです。
子供たちは暖炉のそばに靴下をかけてサンタクロースからのプレゼントを待つ…なんだかとっても夢がありますね!
その後1535年、マルティン・ルターによってこの風習がクリスマスに取り込まれたといいます。
ただこの時点ではサンタクロースはまだ白いひげを生やして赤い服をきてませんし、トナカイとそりも無く、煙突からお家に入ることもしていません。
現在の私たちにお馴染みのサンタクロースの外見や、プレゼントを配る姿は、1823年からなんです。
しかもアメリカの新聞に匿名で寄稿された詩(サンタクロースが来た)が起源であると言われています。
その後1860年~80年代に活躍した漫画家トマス・ナイトが描いた絵を元に、1931年にコカ・コーラ社が広告に赤い服で白髭のサンタクロースを起用したことで、世界中に現在のサンタクロースのイメージが定着したのです。
【 現代でのプレゼント 】

ここでは少しだけ現実的なお話を…
現代のクリスマスプレゼントというと、かなり豪華なイメージがありますよね。
でも以前はごくごく質素なものだったといいます。
11月の終わりからクリスマスまでの期間はアドベントと呼ばれ、教会暦の1つです。
この間はキリストの降誕祭を待ちながら、1日1日と準備を進めます。
キリスト教のカトリックの方たちはこの間祈りと断食をしますし、ドイツではシュトーレン(シュトレン)を毎日ひときれずつ食べる習慣があります。
シュトーレンが初めて文献に登場するのは1474年。
現在はクリスマスの時期になるとシュトーレンを食べる方もたくさんいらっしゃいますが、かなり長い歴史があるんですね。
降誕祭がこんな風に祝われるようになってからしばらくの間は、ごくごくシンプルなプレゼントを贈りあっていたといいます。
たとえば手作りのお菓子であったり、手作りの木彫りのおもちゃ、手作りの手芸品。
16世紀ごろにヨーロッパからアメリカにやってきた開拓者たちは、キリスト教でもプロテスタントだったのでクリスマスの贈り物の習慣はあまり無かったようです。
そして驚くことに17世紀には一時期の間、アメリカではクリスマスのお祝いが禁止されたこともあったとか。
時が流れて18世紀には今のようにクリスマスプレゼントを贈るようになりましたが、それでもまだ今に比べたらシンプルな贈り物だったようです。
今では世界中で一番盛大にクリスマスを祝っていそうなアメリカですが、そんな歴史もあったんですね。
またカナダではもともと、クリスマスの贈り物は元旦に贈りあうのが一般的だったそうなんです。
ですが19世紀に入ると企業側が新年の贈り物をクリスマスに贈ろうと宣伝するようになり、次第にその狙い通り、12月25日にプレゼントを贈る習慣が根付いてきたようです。
企業からしてみれば売り上げを伸ばす絶好のチャンス、だったわけですね。
もともとクリスマスのプレゼントといえば手作りの贈り物を用意するものでしたが、この頃には工業製品が贈り物の主流となり自転車やキッチン用品など、当時手作りできないようなものが人気だったようです。
そして第二次世界大戦後、このプレゼントの豪華さは更に加速します。
そういった流れの中、クリスマスプレゼントとしてのジュエリーやアクセサリーが登場してきたようです。
もちろんご自身へのご褒美として選ぶ方もいらっしゃいますが、ジュエリーやアクセサリーのプレゼントといえば恋人同士を連想する方も多いはず。
恋人同士で贈りあうものであれば
①身に着けることのできるもの(プレゼントを見た時に愛情を思い出せたり、相手を近くに感じられたりするもの)
②邪魔にならないサイズ感(重くなく大きすぎず、毎日使えるもの)
③品質が変化しないもの(すぐに壊れない、変化に強い、消耗しないもの)
こういったポイントが重視されます。
その点、ジュエリーやアクセサリーであれば、①、②はクリアできますし、③も素材によっては問題なしです。
またジュエリーやアクセサリーの中でも、ネックレスやピアス、イヤリングは、指輪のようにサイズがシビアではないので贈り物にしやすいといった点で人気が高いそう。
冬至のお祭りに贈り物をし合う習慣とキリスト教の東方の三賢者(東方の三賢人)のエピソード、そして企業の思惑。
現在ではクリスマスプレゼントには様々な要素が複雑に絡み合ってしまっています。
少々現実的になりすぎてしまいますが、誰かの事を思ってその人のためにプレゼントを選ぶ、からこそ、この現代にも残り続けていると思いたいですね。
【 クリスマスのあれこれ 】
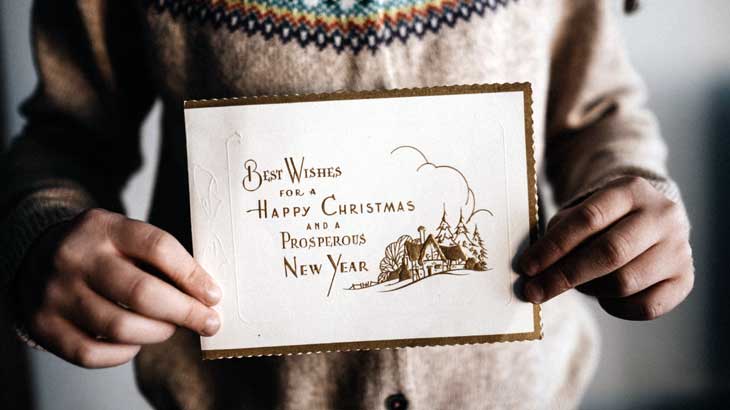
他にもクリスマスにまつわる由来をご紹介。
・クリスマスツリー

この時期になると必ず見かけるクリスマスツリー。
北欧ゲルマン民族の冬至の祭り「ユール」では、樫を飾ります。
この慣習がキリスト教に取り入れられ、モミの木が飾られるようになりました。
これはモミの木が横から見ると三角形に見えるから。
そのシルエットがキリスト教の三位一体(神と子(イエス・キリスト)と精霊は1つの神が3つの姿になって表れた姿であるという考え方。)を彷彿させるためだとか。
「クリスマスの起源」(O.クルマン著)という書籍によれば中世の降誕祭に行われたアダムとイブの舞台劇に使われる「知恵の樹(リンゴ)」は冬の時期には葉が落ちてしまうため、常緑樹のモミの木が代用されたのが始まりとも言われています。
どちらにせよ、寒い季節でも葉を落とさない常緑樹が使われるのがセオリーのようです。
ちなみにツリーに飾るガーランド。
星は先ほどご紹介したようにベツレヘムの星と呼ばれますが、イギリスではクリスマスエンジェルと言われる天使が飾られることもあります。
また現在オーナメントボールと呼ばれるガラスや金属のメッキのボールは、元々はアダムとイブが食べたリンゴを象徴しているんですって。
記録上最古のクリスマスツリーは、1419年ドイツ。
イルミネーションが始まったのは19世紀以降のアメリカが発祥と言われています。
・なんでトナカイは「赤鼻」?

赤鼻のトナカイさん、実は名前もあるんです。
子供から大人まで口ずさめるほどなじみの深いあのクリスマスソング。
主役のトナカイさんはルドルフと言います。
ルドルフは1938年にシカゴで生まれたクリスマスキャラクター。
キャラクターといっても父親が娘のために書いたお話です。
この家族はコピーライターとして働いていた父親、癌になって治る見込みのない妻、十分に甘えることのできない愛娘の3人家族。
娘が父親に「どうして私のママはみんなと違うの?」と疑問を投げかけたことがはじまりなんです。
これを聞いて父親も、自身が小さいころにいじめられた記憶を思い起こし、「みんなと違う」というフレーズを使って娘の為に何かお話しを作ってあげたいと思ったのです。
そして即興で出来上がったのが、赤鼻のトナカイ ルドルフのお話。
その後父親は会社のパーティでこの話を朗読し、大絶賛され、話は冊子となって配布されることになりました。
発行数は250万部。後に再リリースされ、更に350万部の大ヒットを記録しました。
再リリースから2年後、父親のいとこによって作詞・作曲されたのが、私たちの知っているあの「赤鼻のトナカイ」の歌なのです。
「みんなと違う」ことが誰かの役に立ったり、決して悪いことではないということを歌っているあのクリスマスソングには、そんな背景があったのです。
・賢者の贈り物

聖書の東方の三賢者(東方の三賢人)をベースに書かれたのが、小説家オー・ヘンリーの「賢者の贈り物」です。
小説自体を読んだことが無くとも、あらすじは恐らく一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
貧しい若い夫婦がお互いのクリスマスプレゼントを買うために、自身の宝物を売ってしまうというお話。
美しい髪を持つ妻は夫の懐中時計につけるプラチナのチェーンを買うために自身の髪の毛を切って売り、夫は妻の美しい髪に合うべっ甲の櫛を買うために自身の懐中時計を売るというのがあらすじ。
お互いがお互いの為を考えた結果、自身の宝物を失うという、一見なんとも切ないお話。
しかし自己犠牲と相手への愛情こそが「賢者の贈り物」であり、この夫婦はそれぞれに賢者なのです。
形のある物や高価な物だけがプレゼントではないと、改めて考えさせられるお話です。
・日本ではいつが始まり?
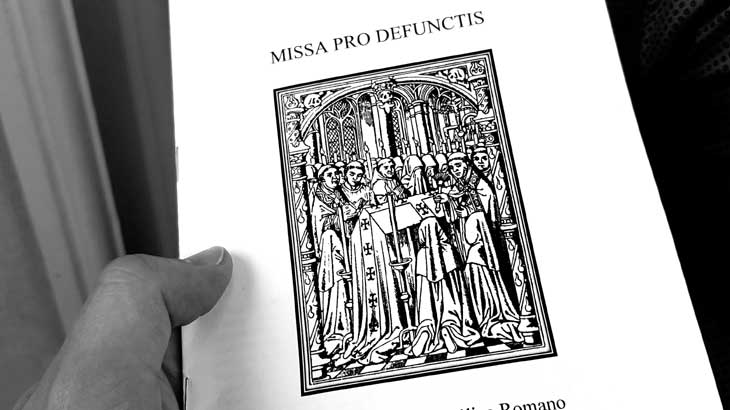
日本でのクリスマスは1522年、現在の山口県でフランシスコ・ザビエルがミサを行ったことが始まりです。
1560年ごろには京都で100人以上のキリシタンが集まるクリスマスの記録も残っていますが、1617年のキリスト教禁止令により開国までの間クリスマスの記録は残っていません。
一般的にクリスマスが浸透し始めたのは明治37年頃から。
銀座に進出した明治屋が当時とても珍しかったクリスマスツリーを店頭にディスプレイしたことが話題となり、クリスマス商戦が始まったというのです。
大正時代にはホテルでクリスマスの晩餐会がひらかれ、日本映画にサンタが登場するようになりましたが、第二次世界大戦により、また姿を消してしまうのです。
戦後にはデパートを中心にクリスマス商戦が活気を取り戻し、日本の景気回復とともに昭和25年ころには一般家庭でもクリスマスを祝うようになっていったようです。
【 まとめ 】

クリスマス に プレゼント を贈るのはなぜ?をご紹介してきました。
歴史的にしっかりとした記録が残っている訳ではないので、わかる範囲内でご紹介をさせていただきました。
少々現実的な思惑の話も入ってしまいましたが、なんにせよ誰かの事を考えながらプレゼントを選ぶ時間は楽しいひと時です。
その相手の喜ぶ顔を見たいから、プレゼント選びにも熱が入りますよね。
今年のプレゼント選びがまだの方は、プレゼントを選ぶときに赤鼻のルドルフや、オー・ヘンリーの「賢者の贈り物」の話を、少しでも思い出してもらえたら幸いです。
プレゼントはすべてが形があるわけではないし、誰かのために何かをするという行為の尊さ、ちょっとした人への気遣い。
自分の大切な人のためにできる何か、が見つかったら嬉しいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
◇アクセサリー モチーフ に込められた意味を知りたい方はこちらをどうぞ→